更新日:2025年1月30日
ここから本文です。
9 降灰に備える
背景と課題
桜島の火山活動
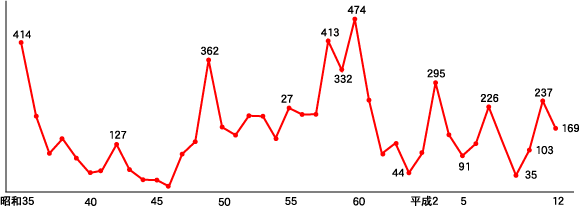
図9-1桜島爆発回数の推移
出典:鹿児島地方気象台
桜島は、1972年(昭和47年)頃から活発な活動を再開、多いときで年に400回以上、現在でも、年200回ほど爆発し、噴煙を高く噴き上げています。爆発は、空震を伴うことが多く、約10kmも離れた鹿児島市でも窓ガラスがビリビリ震え、半開きのドアがバタンと閉まることがあります。
降灰は風向きに左右されます。夏は鹿児島市側、冬は大隅半島や国分、姶良地域に灰が降ります。そこで、鹿児島地方気象台では、桜島上空の風向き予報を毎日出しています。
火山灰の堆積量は、下図の通りですが、粒径は場所によって違います。当然、近距離は粗く、桜島島内では、径1~3mm程度の大きさのものが降り、傘に当たるとパラパラ音がします。鹿児島市内ではもう少し細かくなりますが、時には1mm程度のものも降ります。
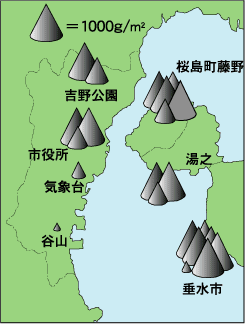
鹿児島県の降灰の住民への影響(平成4年度地域住宅検討調査報告書より)
・降灰に対する意識アンケート対象地域のすべての市町村が95%以上の割合で困っていると回答しています。
・具体的な被害内容(80%以上の割合で困っていると回答した項目
「屋根、雨樋に灰がたまる」「部屋に灰が入る」
「洗濯物が灰で汚れる」「庭木や草花が傷む」
・負担の大きな家事(80%以上の割合で大変だと回答のあった項目)
「住宅や庭の散水」「灰の持ち出し」「部屋の掃除」
「屋根、雨樋の掃除」「洗濯」
注)上記の報告書は、桜島の降灰の影響を受ける地域(鹿児島市、垂水市、桜島町、福山町、輝北町)において住宅金融公庫を利用された方々に対して、アンケート形式による実態調査をもとにしています。
このような降灰の住民に対する影響を効果的に和らげる方法の1つとして、住宅の降灰対策を行います。
対策
→25降灰対策よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください