更新日:2025年8月28日
ここから本文です。
令和7年7月南薩地域の現地農業情報
枕崎市,南さつま市,南九州市
茶摘採技術の腕を競う~知覧茶乗用型摘採競技大会~が開催
7月14日,安全かつ的確な運転操作技術の向上を目的に,知覧茶乗用型摘採競技大会が,南九州市汐見原集団茶園で開催されました。精鋭10チームが参加し,作業時間,安全確認,運転操作の正確さ,摘採面の均一度,機械整備等を茶技術員が審査しました。参加者は安全を確認し,摘採刃の高さを慎重に調整していました。今回は第50回記念大会で,無人摘採機のオープン参加や歴代摘採機の展示もありました。農政普及課は今後も,安全かつ良質な茶生産を支援していきます。
 |
JA南さつま繁殖農家研修会の開催
7月4日,JA南さつま川辺支所にて,JA南さつま繁殖牛農家研修会が開催され,肉用牛繁殖農家9人,関係機関10人の計19人が参加しました。研修会では,JAからEU輸出に伴う使用禁止薬剤の確認と報告について説明がありました。農政普及課は,熱中症・サシバエ対策について研修を行いました。また,管内農家でのスマート機器活用事例,県奨励品種イタリアンライグラス「kyushu1」の情報提供も行いました。農政普及課は,今後もこのような機会を活用して,農家支援を行っていきます。
 |
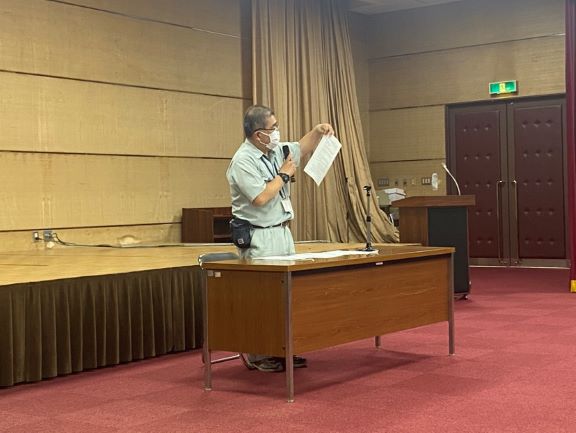 |
サシバエ対策のバーンミーティングが開催される
7月11日,南九州市頴娃町青戸の酪農場で,酪農家,薬品メーカー,県酪農業協同組合,農政普及課の9人が出席し,サシバエ対策のバーンミーティングが県酪農協主催で行われました。サシバエの生態や薬品の昆虫成長制御作用,防虫ネット等について,実際に薬品メーカーが説明し,薬剤散布の具体的な方法などを実演しました。蛹への薬剤防除効果は低いことから,幼虫対策が基本になることを参加者は理解しました。今後も農政普及課は対策を指導していきます。
次代を担うきんかん農家に対する現地ヒアリングを実施
6月13日,20日,27日に就農5年以内及び技術習得支援が必要な農家に対し,園芸振興協議会南薩支部果樹技術部会で現地ヒアリングを実施しました。本年は農家7戸に対し,昨年度の目標収量・階級に対する本人の実績と部会平均値を比較し,反省点と課題について聞き取りと助言を行い,本年度の目標設定と具体的な対策を検討しました。農政普及課は,今後も目標達成に向けて支援していきます。
新規就農者が実践や座学で農業を学ぶ
7月7日と7月17日の2回,農政普及課主催による新規就農者を対象とした農業基礎講座を頴娃農業研修センターで開催し,延べ34人が参加しました。内容は,営農に必要な農業機械,収入保険制度,土壌肥料,病害虫・農薬や農業経営の基礎知識で,農業機械の研修では,熱中症対策やトラクタ・刈払機のメンテナンス等を学びました。また,地域の指導農業士が自らの体験を踏まえ,考える農業を実践する重要性について話がありました。研修生のアンケート結果から,内容を理解できたこと,病害虫対策への関心が高いことが分かりました。
 |
 |
キクハウスの手動式農薬散布装置について意見交換
7月9日,枕崎市大塚地区のキクハウスで,今年度農政普及課が実証検討予定の手動式農薬散布装置の実演会を開催し,実証ほ生産者,メーカー(農薬散布装置施工やノズル),管内のキク生産者等,計9人が参加しました。参加者からは,農薬の散布ムラが少なく,慣行より作業負担の軽減,作業時間の短縮,安全性の向上が図られ,導入による労力や労務費の削減が可能ではないかという意見が挙がりました。今後,実証による手動式農薬散布装置の有効性を検証していきます。
 |
 |
周年菊研究会が土や堆肥づくりを学ぶ
7月24日,大塚公民館で周年菊研究会(枕崎市大塚地区の若手生産者組織)を対象にした土壌肥料の研修会を開催しました。農業開発総合センター普及情報課が「堆肥の影響や正しい使い方」を,メーカーが「大塚地区におけるキクの土壌分析の例年比較と傾向」について説明しました。特に良質な堆肥つくりについては,研修会終了後も熱心な意見交換が行われました。農政普及課は,大塚地区のキク生産者において毎月数十点土壌分析を行っており,今後も分析結果に基づく指導していきます。
 |
周年菊研究会が立神小の花育で出前授業
枕崎市大塚地区の花き生産者は,約30年前から立神小の花育の活動を行っています。7月18日,立神小で,周年菊研究会が5年生を対象に今年度新たに花育の出前授業を行いました。キク栽培に向けた定植前の作業(緑肥のすき込み,太陽熱消毒)について説明し,小学生からは「なぜ緑肥を育てるのか?」「使用したトラクタの金額はいくらなのか?」等,質問が多く出されました。今後は,小学生と12月出しキクの定植・摘蕾・収穫作業や,フラワーアレンジの出前授業を行っていきます。
 |
ピーマン合同研修会で環境制御とIPMを学ぶ
7月8日にJA南さつまの四季彩館で,JA南さつまピーマン部会とJAいぶすきピーマン部会の合同研修会が41人(うち生産者23人)出席のもと開催されました。会では,農業開発総合センター普及情報課から環境制御技術とIPMを含む病害虫防除について,農政普及課から実証ほ成績や根群調査結果の説明と熱中症対策や雇用確保に向けた事業の説明を行いました。農政普及課は,今後も農家の所得向上,産地の維持拡大に向けた支援を継続していきます。
ピーマンの出荷終了 加世田,頴娃地区で反省会が開催
ピーマン出荷反省会が,頴娃地区では7月8日,えい寿ホテルで23人(生産者5戸)が出席し開催され,6年度産実績は106t(単収11.1t/10a)でした。また,加世田地区では7月11日,さんぱるで38人(生産者16戸)が出席し開催され,6年度産実績は397t(単収11.8t/10a)でした。7年度産では頴娃地区で新規栽培1戸,後継者就農1戸,加世田地区で新規栽培1戸,農家研修2戸と若い生産者が増えつつあります。7年度産から共同選果に向けた検討を進めることとしており,農政普及課も支援していきます。
金峰コシヒカリの出荷開始
7月23日にJAさつま日置金峰ライスセンターにおいて,超早場米「金峰コシヒカリ」の出発式が開催され,生産者や関係者およそ50人が参加しました。部会長から,昨今肥料や機械価格の高騰で苦しい状況であるが,米価は昨年と比べて上昇しており,今年の出来も良好であることから期待ができるとあいさつがありました。収穫は7月16日頃から始まっており,7月下旬から収穫が本格的に始まりました。今後も高品質な水稲の生産に向けて支援していきます。
クルクマ主産地交流会IN川辺で活発な情報交換
7月3日,クルクマ主産地交流会IN川辺がJA鹿児島県会館にて開催され,全国の生産者,市場や関係機関が計65人参加しました。川辺の産地事例紹介,各市場の情勢報告,栽培課題や一般消費者への認知拡大をテーマにしたパネルディスカッション(各産地代表者がパネラー)等の情報交換を行いました。翌日には,川辺の現地視察を行いました。今後,生産者,市場,実需者,関係機関等が一体となって「クルクマの日」の制定等,一般消費者へ向けたクルクマの認知拡大に取り組むこととなりました。
 |
 |
帰化アサガオ対策を中心に大豆栽培を学ぶ
7月14日に南九州市川辺支所で大豆の栽培研修会が開催され,19人が参加しました。農政普及課から7月20日までの適期播種,排水対策,昨年多発した帰化アサガオ等の雑草防除体系,中耕培土,開花前の摘心,病害虫対策を中心に説明しました。市からは,極多収品種「そらみのり」の導入助成等の説明がありました。生産者からは,除草体系や収量向上のための質問が挙がりました。今後も収量向上と高品質な大豆の生産に向けて支援をしていきます。
指宿市
観葉の若手農家が地元の生花店を通じて市場動向を学ぶ
6月30日,地元生花店(Ibusuki Botanical Hub 花源)にて生花店の立場から見た消費者ニーズや販売傾向について研修会が開催され,若手農家8人と関係者3人が参加しました。参加者からは「消費者のニーズを知ることで,生産への意欲が高まった」との声が聞かれ,実りの多い研修会となりました。今後も農政普及課では,若手農家の技術力や知識の向上を図るとともに,情報交換や交流の場の継続的な提供をすることで,地域農業を担う若手人材の育成支援を積極的に進めていきます。
指宿地区の肉用牛農家が経営継承・税制を学ぶ
7月17日,いぶすき農業支援センターで,税理士を講師として招き,肉用牛農家を対象に経営継承や税制セミナーを開催しました。当日は肉用牛農家15人と関係機関12人の計27人の参加がありました。講演は相続税額や事業継承のポイント,大中小企業の違い等を講師の経験談を交えた分かりやすい内容で,参加者からは「勉強になった」などの感想が聞かれました。また講演後は個別相談会を行いました。指宿地区は家族経営の肉用牛農家が多いため,将来,円滑な経営継承が行えるよう,技術だけではなく幅広い研修を企画して支援していきます。
JAいぶすきのスプレーギク農家,猛暑対策について意見を交わす
7月11日,JAいぶすき花き部会スプレーギク部門会員が8月出しハウスを5か所巡回し,現地検討会を開催しました。近年,猛暑による開花の遅延が課題となっており,農政普及課では,開花遅延を見越した電照打ち切り日の前進化やハウスの外遮光を推進しています。当日は各ハウスの気温データと実際のキクの開花状況を確認し,ハウス妻面を解放して風通しを良くすることや,外遮光資材を被覆する等,気温上昇を抑えると開花遅延しにくいことを部会全体で確認することができ,有意義な検討会となりました。
いぶすきマンゴー出荷最盛期に果実品質を競う
7月28日,JAいぶすき旧大山支所2階大会議室で,JAいぶすき熱帯くだもの部会が「第20回M-1グランプリ」を開催しました。今年産のマンゴーは,昨年晩秋期の高温と2月の寒波による影響で生育が2週間程度遅れたものの,除湿対策や高温対策の適切な実施により品質・収量ともに平年並みに仕上がりました。出品された10点は,外観が良く糖度も15度以上と甲乙付けがたい高品質のマンゴーが揃っていました。今後も農政普及課は,難防除害虫対策や晩秋期の新梢抑制対策を徹底し「いぶすきのマンゴー」ブランドの確立のため指導を徹底していきます。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください