更新日:2025年12月9日
ここから本文です。
農作業安全の手引き(安全快適な作業条件設備)
安全で快適な作業環境整備
1暑熱環境
夏季の炎天下での作業は体温調節のバランスが崩れ,熱中症(熱射病,熱けいれん,熱まひ)を生じたり,皮膚の弱い人は日焼けによって火傷のような症状になることもあるので,次の事項に配慮する。
- 日中の気温の高い時間帯を避けて作業を行うなど,無理のない作業スケジュールを立て,十分な休憩ができる休憩場所を確保し,こまめに水分摂取や,汗で失われた塩分補給(0.1~0.2%の食塩水や梅干・味噌等)を行う。
- 作業場所に日よけを設けるなど,できるだけ日陰で作業を行う。
- 屋内では遮光や断熱材の施工等により,施設内の温度が上がらないようにするとともに,風通しをよくし,室内の換気に努める。
- 施設内に熱源がある場合には,熱源と作業者との間隔を空けるか断熱材で隔離し,加熱された空気は屋外に排気する。
- 作業服装は通気性や吸湿性がよく,首や手足が開放的な作業着と帽子を着用する。
- 夏は涼しく作業ができるよう保護衣等を利用する。ファン付き作業服,クールチョッキ,クールキャップ,ネッククーラー,UVカット素材を用いた作業着遮光ネットを活用した日みの,網シャツ等
2寒冷環境
冬季の気温の低い環境での作業は,10℃以下になると末梢毛細血管の収縮により手作業の能率低下や誤りが多くなったり,体がこわばって動作がぎこちなくなり思わぬ事故を起こすことがあるので,次の事項に配慮する。
- 朝夕の気温の低い時間帯を避けて作業を行い,こまめに休憩を取って体を温め,寒いところでの作業時間を短くする。
- 保温性の高い素材の作業衣や防寒手袋を着用する。
- 作業場の床材がコンクリートの場合はカーペット,板等を敷く。
- 電気ストーブ等で足元を暖かくする。
3ハウス内作業
冬季のハウス内作業は,ハウス内と外気の温度差が5℃以上になるため,体温調節機能がうまく働かず頭が重い,だるいなどのハウス病を引き起こす恐れがある。また,夏季のハウス内作業は,高温により熱中症を引き起こすことがあるので,次の事項に配慮する。
- 体調がすぐれない時,ハウス内の温度が著しく高い時はハウス内作業を避ける。
- ハウス内の高温対策としてハウス内外に遮光ネット等被覆資材を利用する。
- 冬季のハウス内外の温度差を少なくするため,ハウス中に中間気候室を設けハウス内外の中間温度を設定する。
4粉塵・アレルギー
農薬や花粉,毛じ,脱穀・乾燥時の粉塵,樹液などによる鼻炎,喘息,皮膚炎などの対策として,次の事項に配慮する。
- 農薬散布時は十分な服装装備を行う。
- 収穫作業には収穫車等を利用し,作物との接触を避ける。
- 収穫・調製作業時の粉塵対策として,換気と換気扇の設置,マスク・手袋の着用,手洗いの励行を行う。
- 作業終了後には着替えを行い,うがい,手洗い,洗眼(顔)をする。
5騒音
一般に農業機械の騒音は80~100dB(デシベル)の間にあって,平均で90dB前後である。普通85dB以上の騒音は改善対策を要し,長時間の騒音にさらされると,難聴や作業能率低下,睡眠障害,自律神経障害,内分泌障害としてホルモンの増加や減少,胃腸の消化低下等の悪影響がある。安全対策として,次の事項に配慮する。
- 機械の導入は,できる限り騒音の少ない機械を選定する。
- 騒音源と作業者を隔離するため機械の配置を変える。
- 騒音源にカバーをかけ,低騒音化や原因の除去を行う。
- 適当な間隔で休憩や交替を行い,長時間の騒音下での作業を避ける。
- 耳栓,イヤーマフ等の保護具を着用する。
騒音の暴露許容時間
| 1日の暴露時間 | 騒音レベル |
|---|---|
| 16時間 8時間 4時間 2時間 1時間 30分 15分 7.5分 |
80dB 85dB 90dB 95dB 100dB 105dB 110dB 115dB |
振動は大きく分けて,トラクタやコンバイン等の乗用型農業機械を運転している場合に全身に感じる全身振動と,刈払機を使用しているときに手に感じる手腕系振動がある。全身振動の繰返しによる胃腸障害,腰痛等や,手腕系振動による血行障害で手のこわばり,しびれ,痛み等の障害を起こすことがあるので,次の事項に配慮する。
- 機械の導入は,できる限り振動の少ない機械を選定する。
- 適当な間隔で休憩,交替を行い,著しい振動のある作業場での連続作業を避ける。
- 振動が低くなるエンジン回転で作業を行う。
- 機械をこまめに整備し,摩耗した部品を交換する。
(刈払機の使用)
- 刈払機使用は20分以上の連続作業を避け,1日2時間以内の作業とする。
- 振動に寒冷が影響するので,気温が10℃以下の時は作業を避ける。
- 冬季の作業では,体の保温に気をつける。
- 防振手袋等の保護具を着用する。
- 騒音対策に耳栓・イヤーマフ等の保護具を着用する。
- 作業終了後は入浴し,手や腕のマッサージをする。
7明るさと色彩
農作業を快適に能率よく安全に実施するためには,適正な照度の確保や調製作業時の視対象物と作業面の配色の工夫等が必要である。
- 調製作業では普通500から1000ルクスの照度が必要で,高齢者では視力低下を考えて,通常より2~4割程度照度を上げる。
- 局所照明だけに頼ると目が疲労するので,局所照明の1月10日以上の全般照明を併用する。
- 北向きの窓は直射日光は入らず1年中平均した明るさが得られる。
- 目より上方の壁や天井は,照明効果を良くするため明るい色がよい。
- 収穫物と作業台の色が似ていると目が疲れ,作業しにくい。たとえばイチゴのパック詰め作業では,作業面を無彩色のグレーにする。
年齢別必要照度の倍率
| 視力 | 年齢(歳) | |||
|---|---|---|---|---|
| 20歳 | 50歳 | 60歳 | 70歳 | |
| 1.0 | 1倍 | 1.4倍 | 2.5倍 | 3.8倍 |
| 1.2 | 1倍 | 1.5倍 | 2.7倍 | 3.5倍 |
| 1.5 | 1倍 | 1.6倍 | 2.3倍 | 2.9倍 |
重い荷物の運搬は,転倒や腰痛等の原因となるので,次の事項に配慮する。
- 荷物を分割,複数での運搬,運搬車の利用等により,なるべく負担を少なくする。
- 運搬車,運搬ローラー設置,キャスター付き運搬車を使用する。
- 重い物の持ち上げ方は,荷物を体の正面近くに寄せて膝を使ってゆっくりと上げ下げする。
- 抱えやすい容器の使用や取っ手を付けるなど持ちやすくする。
- 腰痛予防ベルトを着用し腹筋,背筋を支え腰痛を予防する。
- 通路は段差や障害物をなくし,作業しやすい幅を確保する。
重量物運搬制限の目安
| 運搬方法 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 一 回 |
手かかえ | 25kg | 20kg |
| 肩かつぎ | 50kg | 30kg | |
| 重 量 |
断続作業 | 30kg | |
| 連続作業 | 20kg | ||
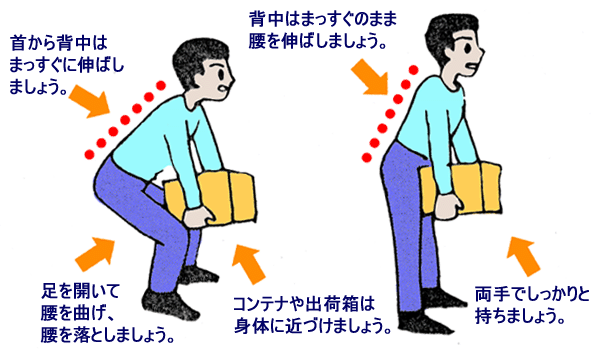
9作業姿勢
著しく腰を曲げる等のきつい姿勢での作業や長時間同じ姿勢を続ける作業は,首,肩,腰等へ疲れが集中し,肩こり,腰痛等の原因や事故の要因ともなるので,次の事項に配慮する。
- 無理な作業姿勢(前屈姿勢,ねじり姿勢,かがみ姿勢,伸びる姿勢)を減少させる。
- 同一姿勢作業の継続を避け,他の作業と組み合わせる。
- 作業者の身体にあった作業台とイスの高さを設定する。
作業台,いすの高さの設定
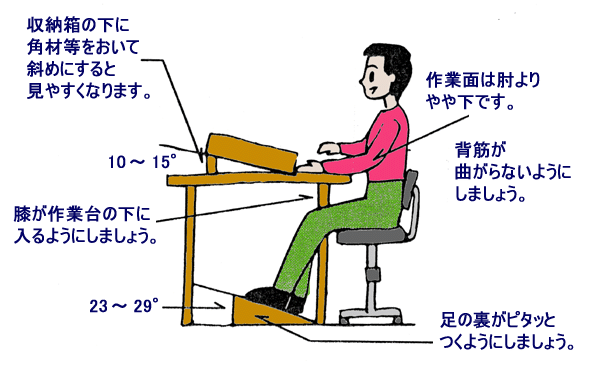
10農業機械の使用
事故の発生の要因は,(1)機械の整備不十分,(2)作業計画の不適切,(3)農地・農道の不適正,(4)労働者の非正常(未熟,睡眠不足,過労,イライラ状態等)があり,機械作業の安全性の確保について次の事項に配慮する。
(農業機械の取扱い)
- 体調が悪いときは,運転作業をしない。
- 機械の取扱い説明書や安全対策のパンフレットを良く読む。
- 作業前の機械の点検,安全に対する注意を徹底する。
- トラクタに安全フレーム,安全キャブを付ける。
- 運転作業時は裾,袖口が締まっており,働きやすい作業衣を着用する。
- 長時間の運転作業は避ける。(2時間作業に10~20分休憩)
- 高齢になってくると操作以外に配慮する余裕が無くなって来るので,作業速度によっては役割分担を見直す。
- 著しい騒音がある場合は,耳栓・イヤーマフ等の保護具を着用する。
- 著しい振動がある場合は,防振手袋や防振グリップ等の保護具を着用する。
- 道路走行時は,目立つように低速車マークや反射マークを貼る。
- 緊急時に備え,作業機械の動力遮断方法やエンジンの停止方法を家族や作業者全員が確認しておく。
- 広大な農地での1人の作業は,事故時の救援依頼が困難になりがちであるため,携帯電話を携帯する。
(周辺環境)
- ほ場出入口の幅を広げ,スロープを長くして傾斜を緩くする。
- 路肩がわかりやすいように畦畔の草払いを行う。
11農薬散布作業(適正な農薬使用の指導指針抜粋)
県環境と調和した農業確立推進本部
(農薬散布前)
- 使用前に必ず農薬のラベル(説明書)に記載されている適用作物,対象病害虫,使用方法,使用回数,収穫前日数などを確認し,これを厳守すること。また,最終有効年月を過ぎた農薬は使用しないこと。なお,不明な点は,農業団体や市町村,県等に相談すること。
- 使用回数については,「生産に用いた種苗の播種又は植え付け(準備作業を含む)から収穫までの有効成分毎の総使用回数」であるので,十分注意すること。
- マスク,手袋,帽子,長靴,防除着(防水)はあらかじめ準備しておき,これらを適正に使用して,農薬を浴びない(吸入しない)ように散布すること。
- 防除器具は,使用前にも洗浄を徹底すること。
- 健康に留意し,体調の悪い場合は散布作業を避けること。
a飲酒後や睡眠不足等で疲労している場合
b体力,特に肝機能が衰えている場合
c手足などに外傷がある場合
d妊娠,生理中の人
e特異体質の人(アレルギー体質,かぶれやすい人)
- 河川等の汚染や通行人などに被害を及ぼさないよう,また,漂流飛散(ドリフト)がないよう,散布前に周辺環境や気象状況等を十分把握すること。
- 学校,病院や住宅に接した地域,養蜂が行われている地域で農薬を使用するときは,あらかじめ付近の住民や関係者へ連絡するなど,危被害やトラブルが発生しないように十分配慮すること。
(農薬調製・散布時)
- 必要以上の農薬の調製は避け,散布後に薬液が残らないようにすること。
- 散布ほ場等に散布者以外が近づかないように配慮すること。
- 農薬の調製等取扱には十分に注意し,慎重に行うこと。
- 風向きを考え,農薬の使用者はもちろん,住宅,通行人,畜舎などに直接かからないようにすること。特にパイプダスターで粉剤を散布する場合は,中持ちをしないこと。
- 夏場における日中の散布は,散布者の体力の消耗が激しいばかりでなく,作物にとっても薬害がでやすいので,作業は日中の暑い時間帯を避け,朝夕の涼しい時間帯に散布等を行うこと。
- 施設内で農薬を散布する場合には,施設内に充満し,作業者の体に付着したり,吸入し易くなるので,必ず専用の防毒マスクを着用すること。
- 農薬が体に付着した場合は,石鹸水で十分洗い流すこと。
- 防除作業に対する慣れ・油断は禁物であり,農薬の粗雑な取扱いは慎むこと。
- 2種以上の農薬を同時に散布する必要がある場合は,原則として混合剤を使用すること。ただし,混合剤がない場合は,「農薬混用事例集」等を参考にすること。
(散布作業終了後)
- 農薬の調製や散布に使用した器具はよく洗浄し,洗浄水等が,河川等へ流れ出ないよう十分注意すること。
- 万が一,農薬が残った場合には,容器を密閉・密栓し,冷暗所に施錠保管すること。
- 手足を石鹸水で十分洗い流し,衣服は下着まで取り替え,着用した衣服は速やかに洗濯すること。
- 作業後の飲酒,夜ふかしは慎むこと。
- 少しでも気分が悪くなった場合は,医師の診断を受けること。その際は,必ず使用農薬名など散布作業の内容を告げること。
- 防除日誌に病害虫の発生状況と併せ,農薬を使用した年月日,場所,農作物,種類又は名称,単位面積当たりの使用量又は希釈倍数等を記帳すること。
- 種子・種苗消毒に伴い農薬残液が大量に同時期に発生する場合,農薬残液の凝集又はろ過が可能な産業廃棄物処理業者等に処理を依頼するか,自らが農薬残液処理施設を利用し,適正に処理すること。
(農薬の保管)
- 保管場所は冷暗所とすること。
- 必ず施錠できる専用の保管庫で管理し,紛失,盗難にあった場合は,直ちに警察署等に届けること。
- 開封後の農薬は,必ず密閉・密栓してあることを確認し,保管管理すること。
- 農薬の移し替え(清涼飲料水の容器等)は,絶対に行わないこと。
- 揮発性の高い農薬は,住居や住居に隣接する建物では保管しないこと。
(不要になった農薬等の適正処理)
不要になった農薬,変質して使えなくなった農薬,最終有効年月の切れた農薬は,みだりに廃棄せず,専門の処理業者に処分を依頼すること。
12クロルピクリン剤使用時の留意事項(クロルピクリン安全使用指針(H14制定))
- 周辺の人や家畜等に対する被害防止対策について
ア住宅,畜舎等に隣接しているほ場や,地形や風向き等を勘案して人畜に被害を及ぼす恐れがあるところでは使用しない。
イ炎天下や,土壌が乾燥しているときは,注入したクロピクリン剤が気化しやすく,地上への拡散も速くなるため使用しない。
ウガス化したクロルピクリン剤は空気より重いため,無風状態のときはガスが停滞する恐れがあるので使用しない。
エ注入後は直ちに穴をふさぎ,地表面をポリエチレン又は塩化ビニールフィルム等で必ず被覆し,風等で剥げないよう周辺をしっかりと覆土する。
オ作業中及び被覆している間は,危険なことを知らせる赤旗等を立て,子ども等がほ場に近寄らないようにするとともに,定期的にほ場を巡回して,被覆シートの破れ等によるガス漏れがないか確認する。
カ被覆シートの除去作業は,臭気が残っていないことを確認したうえで行う。
キクロルピクリン剤は,冷暗所の必ず鍵のついた専用の保管庫で管理するとともに,紛失,盗難にあった場合は,直ちに警察署に届け出る。
ククロルピクリン剤の保管及び使用中に,ガスの漏出など人畜に危害を及ぼす恐れが生じたときは,直ちに保健所,警察署,消防署に届け出るとともに危害を防止するために必要な措置を講じる。
- 使用者の安全対策について
ア必要量を計画的に購入し,薬剤が残らないように使い切る。
イ容器に示してある使用方法や注意事項をよく読んで使用する。また,初めて使用する場合は,農協,地域振興局・支庁の農政普及課,たばこ耕作組合等関係機関・団体の指導を受ける。
ウ高温になるとガス化するので,夏場の作業は涼しい時間帯に行う。また,クロルピクリン剤は使用前によく冷やしておき,取扱中も容器に直射日光が当たらないように工夫する。
エ作業に当たっては,防護マスク,保護メガネ,ゴム手袋などをつけ,風向きに注意し,風下から風上に向かって作業する。
オ作業後は,顔,手足等皮膚の露出部を石けんでよく洗い,必ずうがいを行う。
カ使用した注入器具等はすみやかに灯油等で良く洗浄する。
キ使用済み容器は,蓋を取って上部や側面に穴を開け,注入したほ場内に逆さまに埋めておき,臭気が抜けた後,ほ場から回収し,廃棄物処理業者に委託して処理する。
- 応急処置等
ア皮膚に付着すると,水疱を生じることがあるので,直ちに拭き取って,多量の温湯や石けん水でよく洗浄する。
イ目を痛めたときは,多量の水で15分以上洗い流し,ひどい場合は直ちに眼科医の手当を受ける。軽度の場合は,目をこすらないように注意する。
ウ胸が苦しくなったり,気分が悪くなるなど異常が生じた場合は,直ちに医師の手当てを受ける。
農薬散布時の服装
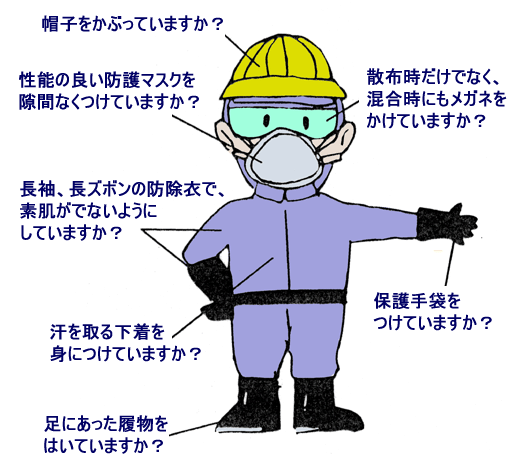
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
窓口でのお問い合わせは行政庁舎11階までおこしください
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください