ホーム > くらし・環境 > 住まい > 環境共生住宅 > 方針1:省エネルギー > 風を活かして快適に暮らす > 3 地域の風を活かして快適に暮らす
更新日:2025年1月30日
ここから本文です。
3 地域の風を活かして快適に暮らす
背景と課題
普段は穏やかな地域の風
風は、まちや住まいの熱や汚染物質を移動したり、海から塩分を含んだ空気を運んでくる等、私たちのまわりの空気の状態と密接に関係しています。また、風があたると人の体感温度は変化し、夏期においては心地良い涼感をもたらしてくれます。風をうまく制御し、活用することで、快適な居住環境の形成に役立てることができます。このような風は、地球規模の気圧配置によって発生する季節風や台風、地域の地形の影響を受けて発生する山谷風や海陸風等が合わさり、更に、建物群や山林等の地表の状況の影響を受けながら形成され、出現します。また、地表面から上空まで高度ごとにも異なった挙動を見せる、とても複雑でデリケートなものです。そのため、鹿児島県内各地域によって吹く風にはそれぞれに特徴があります。風を役立てるためには、地域の風の性状を良く理解し、適切な方法を採用する必要があります。
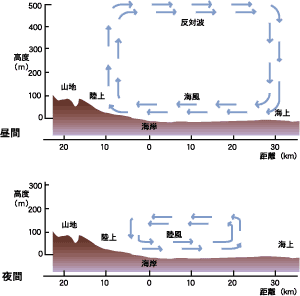
図3-1昼夜間における海陸風の循環モデル
富民協会「風を読む」より作成
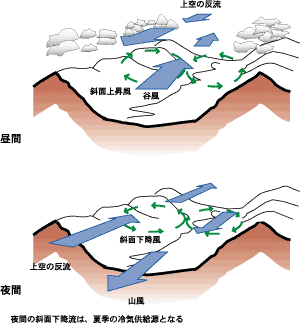
図3-2谷の下から見た山谷風循環の模式図
「建築設計資料集成」より作成
普段は穏やかな鹿児島県の風
鹿児島県の全体の年間平均風速は2.4m/sです。この年間の平均値を超える県内のアメダス観測地点は薩摩南部地方では枕崎(4.0m/s)、北部地方では阿久根(3.3m/s)等の沿岸地域、または島嶼部です。内陸部や鹿児島湾周辺の地域では、平均値を下回る穏やかな値になっています。また、各地域の風向も、地形等の影響を受け、様々です。
| 風速(m/s) | 陸上 | 海上 |
| 0.1~0.2 | 静穏、煙はまっすぐに昇る | 鏡のよう |
| 0.3~1.5 | 風向は、煙がたなびくので分かる が、風見には感じない |
さざなみ |
| 1.6~3.3 | 顔に風を感じる。木の葉が動く。 風見も動き出す。 |
小波、波頭は滑らか |
| 3.4~5.4 | 木の葉や細かい小枝がたえず動く、 軽い旗が開く |
小波、ところどころ白波 |
表3-1ビューフォート風力階級表
富民協会「風を読む」より作成
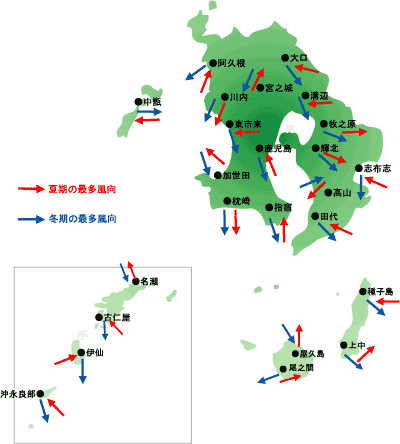
| 年間平均風速(m/s) | |||
| 鹿児島県全体 | 2.4 | 輝北 | 2.1 |
| 阿久根 | 3.3 | 志布志 | 1.6 |
| 大口 | 1.4 | 高山 | 2.2 |
| 宮之城 | 1.3 | 田代 | 1.4 |
| 川内 | 1.4 | 種子島 | 4.8 |
| 牧之原 | 1.7 | 上中 | 3.8 |
| 中甑 | 1.8 | 屋久島 | 3.9 |
| 東市来 | 2.0 | 尾之間 | 3.4 |
| 鹿児島 | 1.7 | 名瀬 | 2.4 |
| 加世田 | 1.6 | 古仁屋 | 2.4 |
| 枕崎 | 4.0 | 伊仙 | 3.0 |
| 指宿 | 1.6 | 沖永良部 | 5.5 |
図3-3年間平均風速と最多風向
出典:気象庁「1979~2000年気象庁観測所及びアメダスデータ」より作成
ただし風向データは1996~2000年
風も自然の恵みのひとつで、使い方によっては有効なエネルギーになります。鹿児島県の年間の平均風速は、島嶼地域や沿岸地域では3~5m/sと大きく、風力の活用が考えられます。その他の地域でも風を巧みに活かした暮らしが実現できます。そのためには、地域を流れる季節の卓越風向や風速等、風の特徴を良く理解し、夏は涼しい風を上手に取り込み、冬は厳しい風を防いで快適な暮らしをつくることが大切です。
対策
→06建物配置による風のコントロール→07植物による風のコントロール
→08建物形状や開口部による室内の風道の確保
→09風力発電の利用
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください