ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農業農村整備 > 地域の話題(現場トピックス) > 農業農村整備現地トピックス(令和6年7月)
更新日:2024年11月11日
ここから本文です。
農業農村整備現地トピックス(令和6年7月)
平板測量競技会(南薩地域振興局)
 7月12日に加世田常潤高校で平板測量競技会が開催され,当課から6名,土改連から4名が審査員として参加した。会には県内の3高校から7チームが参加し,小雨の中,生徒は全国大会を目指して真剣に競技に取り組んでいた。我々も慣れない測量の審査ではあったが,無事に終えることができた。優勝した鶴翔高校Aチームには全国大会での活躍を期待したい。
7月12日に加世田常潤高校で平板測量競技会が開催され,当課から6名,土改連から4名が審査員として参加した。会には県内の3高校から7チームが参加し,小雨の中,生徒は全国大会を目指して真剣に競技に取り組んでいた。我々も慣れない測量の審査ではあったが,無事に終えることができた。優勝した鶴翔高校Aチームには全国大会での活躍を期待したい。
スマート農業基盤整備モデル事業打合せ(南薩地域振興局)
7月8日,南さつま市役所で本庁農地整備課農村計画係,南薩農村整備課,南さつま市耕地林務課,金峰町土地改良区の4者で,現在南さつま市金峰町で計画されているスマート農業基盤整備モデル事業を円滑に推進するための打合せを実施した。本取組は,スマート農業の実装に向けて設計から施工まで3次元データを活用して行う先進的なものである。令和7年度からの事業実施に向けて,施工同意取得や地域計画との整合など,関係機関や非農業者を含む関係者と丁寧に合意形成を図っていく必要があると感じた。
現場技術検討会(北薩地域振興局)
7月23日,更新工事等を実施中である伊唐島地区(斜張橋L=675mの橋梁補修工事),福ノ江地区(口径1,350mmの排水ポンプ更新工事)及び阿久根北部(防災重点ため池の堤体改修工事)の各工事現場において現地技術検討会を開催した。
当日は,鹿児島局や姶良・伊佐局の若手農業土木職員も検討会に参加し,技術的な面や施工方法などに関して活発な意見を交わすとともに交流を深める良い機会となった。
ため池管理システム導入に伴う合同現地研修(姶良・伊佐地域振興局)
7月24日に霧島市溝辺町竹子地内に位置する栗下池において,ため池管理システム導入に伴う合同現地研修会が開催された。霧島市では,栗下池と他2池に監視システムの導入を予定しており,当日はメーカーによるシステムの説明があった。
今回のシステムは,水位センサーとカメラを設置し,Bluetoothでソーラーパネル一体型のルーターと繋ぎ,ため池を遠隔監視するシステムである。Webアプリで水位と画像をいつでも見ることができ,溝辺支所でデモ用PCから現在の池の様子を確認した。また,鳥取県や大分県では約50箇所で今回のシステムを導入しているとの実績紹介もあった。
畑地かんがい工事研修会(曽於畑地かんがい推進事業センター)
7月24日,曽於土地改良会館にて畑地かんがい工事研修会を実施した。研修会には管内の工事関係者のほか,他管内からの県職員も含めて約40名が出席した。研修会は当課の各担当者から施工計画書の作成,パイプライン工事の施工に伴う留意点,試験施工の目的と工事書類の簡素化,事業全般について説明を行った。本研修会を通じ適切な現場運営,施工・管理体制を整え,農業農村整備事業が地元から喜ばれるような工事となるよう努めていきたい。
畑かん事業・畑かん営農担当者研修会(曽於畑地かんがい推進事業センター)
7月26日,曽於南部土地改良区で畑かん事業・畑かん営農推進担当者研修会が開催された。これは本年度新たに曽於地域の畑かん事業,畑かん営農に従事する県,市町,改良区等の職員を対象に,曽於地域の畑かん事業の概要や畑かん営農推進の取組,散水器具の種類,取扱い等について学ぶもので,実際の散水器具を用いた散水実演会も行われた。実演会ではロールカーや噴射ホースによる散水など初めて見る職員も多く,活発な質疑応答が行われた。本研修会を通じて曽於地域の畑かんについて理解を深め,今後の畑かん営農推進に生かしたい。
地域密着研修について(大島支庁)
7月22日,29日に,地域を深く知ることによって業務に対するモチベーションを向上させることを目的として,大島支庁職員を対象に,地域密着研修会が開催され,農村整備課職員が講師を務めた。
研修では,「奄美大島の自然と生き物について」というテーマで,奄美大島に生息する希少動植物や関係法令,「奄美大島・徳之島公共事業における環境配慮指針」等について紹介した。
周知のとおり,奄美大島は世界自然遺産に登録された豊かな生態系を有しており,公共事業を実施する際には,自然環境への配慮及び工事による負荷の低減が求められる。
将来に渡って奄美の自然と農業が共存できるように,実際に工事を計画・実施する際には,関係法令等を遵守していきたい。
農整マスター塾(徳之島事務所)
7月9日から11日までの3日間,令和6年度農整マスター塾が徳之島で開催された。22名が参加し,初日は徳之島管内のほ場整備や末端散水施設の現地研修を行い,2日目は室内研修,3日目はほ場整備計画地区の現場研修を行った。当課職員が講師となった現地研修では,末端散水施設のリレー制御等に多数の質問があり,参加者の熱度の高さがうかがえた。機会があれば再度の徳之島開催に協力したい。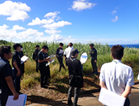
畑かん営農推進協議会研修会(沖永良部事務所)
7月25日,沖永良部地下ダム中央管理所において,沖永良部島畑地かんがい営農推進協議会主催の「畑かん営農推進研修会」が開催され,管内の町,改良区,土改連,県の担当者約40名が参加した。
研修会では,農業普及課から「沖永良部島の主要品目と作型」,農村整備課から「農業農村整備事業の流れ」,農業開発総合センター徳之島支場から「沖永良部島の土壌特性とかん水の効果」,土地改良区から「散水器具の種類と使い方」の研修があった。
今後とも関係機関と連携しながら畑かん営農を推進していきたい。
令和6年度農業土木技術職員中級研修を開催(農地保全課)
7月24日から26日にかけての3日間,おおむね入庁8年目未満の職員8名を対象に鹿児島県土地改良事業団体連合会の職員と合同で中級研修を開催した。
水田ほ場整備の調査,測量,設計業務を通して,これまで習得した農業土木技術の確認を行うとともに,同世代間のコミニケーションの機会を深め,中堅職員として農業土木技術の研鑽を積む良い機会となった。今後も技術研修会の開催を通じて,職員の人材育成・技術力向上に努めたい。
農業農村整備事業の技術力向上に繋がる発表会を開催(農地保全課)
7月25日,市町村自治会館において令和6年度農業農村整備事業技術発表会を開催した。
昨年に引き続き,Webと対面を併用したハイブリッド方式で開催し,計481名の参加があった。当日は各出先機関の担当者をはじめ,市町村,土改連及びコンサルタント等から,それぞれの工事や業務において工夫した点や活用した技術,新たな取組などについて,13事例の発表があり,今後の農業農村整備分野の技術力向上に寄与する発表会となった。
今後も技術発表会等の開催を通じて,技術力の研鑽に係る機会の創出に努めたい。
災害派遣情報(福岡県朝倉市)
令和6年4月1日付けで福岡県朝倉市役所農地等・林道災害対策室に災害派遣で行っております東です。
現在,令和5年災で被災した農地・農業用施設の早期復旧に向け業務に取り組んでいるところです。R5災は,簡素化査定(条件付き査定)で受けているため,主な業務としては重要変更のための資料作成を行っています。件数が多く発注まで至っていない状況ですが,農家さんが少しでも早く営農を再開できるよう早期復旧に務めていきたいです。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください