ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農業農村整備 > 地域の話題(現場トピックス) > 農業農村整備現地トピックス(令和6年12月)
更新日:2025年3月6日
ここから本文です。
農業農村整備現地トピックス(令和6年12月)
棚田等保全活動支援事業(後岳棚畑)そば打ち活動(南薩地域振興局)
12月8日,南九州市知覧町の後岳棚畑において,組織会員や南九州市耕地林務課職員,南薩地域振興局農村整備課職員2名でそば打ち活動が行われた。今回のそばは,9月1日に当棚畑で植えられたそば粉が使用された。
当課職員も,組織の先生に指導を受けながらそば作りを体験し,なかなか見栄えの良いそばを作ることが出来た。また,活動後には試食会も行われ,そば粉100%のそばを頂き,地域の方々と交流を楽しむことができた。
鶴翔高校現場見学会(北薩地域振興局)
12月5日,阿久根市主催で鶴翔高校(総合学科環境緑地系列)2年生7名を対象とした現場見学会が行われ,農村地域防災減災事業(農村災害)阿久根北部地区の現場(八郷排水路及び中面ため池)について北薩地域振興局農村整備課職員が説明を行った。
参加者からは工事費や材料,工期などについて活発な質問があり,有意義な現場見学会となった。
今回の見学会が将来の若手技術者の確保,さらには技術力継承等の一助になれば幸いである。
北薩地区専門高校フェスタ2024(北薩地域振興局)
12月11日,薩摩中央高校において,北薩地区専門高校フェスタ2024が開催された。
本イベントの参加者は主に中学生で,北薩地区の普通科以外の学科がある高校の各ブースでの説明に参加者は熱心に耳を傾けていた。
翌年度は,鶴翔高校から農業土木のPRを県と一緒に行いたいと打診されており,中学生の進路先に農業土木を選択してもらえるような企画を検討してまいりたい。
令和8年度新規採択要望川東地区事業説明会(姶良・伊佐地域振興局)
12月1日、姶良市蒲生町川東中公民館で開催された令和8年度新規採択要望地区の川東地区事業説明会に出席した。
会では,所有者及び耕作者約30名に向け、姶良市より事業導入経緯や工種内容、事業負担金等の説明が行われた。本地区は地元負担軽減のため促進費の活用を見込んでいるが、出席者から促進費の有用性や集積に関する質問等が挙がった。
今回の説明会を契機に更なる事業への理解を得るとともに,関係期間とも密な連携を図り,事業採択に繋げていきたい。
管内初となる高病原性鳥インフルエンザの発生(姶良・伊佐地域振興局)
12月19日,本年度の本県2例目となる高病原性鳥インフルエンザが霧島市福山町の農場で発生した。今年度から鳥インフルが発生した場合,埋却作業の初動から埋却完了までを農業土木職員が担うことになっている。そのため,鳥インフルの陽性判定が出てすぐに埋却予定地に向かい,地元建設業協会の方と現場を確認し,翌朝から埋却地の掘削を開始した。
当管内で初めての発生ということで,地元建設業協会の方々も試行錯誤での作業ではあったが,協力し合いながら無事業務を完了することができた。
最後に,当管内で発生した鳥インフルの埋却作業について,農業土木職員全員で協力して対応していただいたことに改めて感謝申し上げたい。

スマート農業機械実演会に参加(熊毛支庁)
12月3日と4日,種子島において農政普及課主催のスマート農機の実演会が開催され,熊毛支庁農村整備課の職員4名が参加した。
実演会では,スナップエンドウの防除作業を自動で行う機械の実演があり,一度設定すれば基本的に人の操作は不要であるが,監視のための人員は必要との説明があった。
参加した農業者から畝間の間隔やターンするための必要幅などの質問があり,農業者のスマート農機への関心の高さがうかがえた。
今後,スマート農業等に対応した基盤整備事業の推進に役立てたい。
水利施設はみんなで管理しよう!(屋久島事務所)
12月12日から23日,中山間地域総合整備事業屋久地区の地元説明会の後,水利施設の管理方法の説明を行った。屋久島では,水利組合などの組織が設立されていない施設が多く存在している。今後持続可能な農業を進めていくためには,管理作業に利用者の多くが関わる仕組みを作る必要があるため,日常管理を行う必要性と,水利組合設立の説明を行った。農家の中には水利施設を誰がどのように管理しているのか知らない方が多く,今後の維持管理について地元で話し合う良い機会となった。
今後もこのような機会を設け,円滑な事業推進に努めたい。
沖縄県との農業農村整備事業交流(大島支庁)
12月19日,奄美群島農業農村整備事業推進協議会は,気候・地勢・土壌など奄美群島と同じような条件の沖縄県と,農業農村整備事業について相互に学ぶため,交流研修を実施した。
研修では県営や国営事業により整備された長浜ダム(読谷村)や慶(ぎー)座(ざ)地下ダム(八重瀬町)における水利用実施状況,グリーンベルト設置による赤土等流出防止対策事例(糸満市)の視察や沖縄県土地改良事業団体連合会との情報交換も行った。
今後も沖縄県との情報交換を行い,奄美群島の農業・農村の更なる振興に寄与したい。
喜界第二地下ダムに関する検討状況説明会及び意見交換会(喜界事務所)
12月3日,九州農政局喜界島農業水利事業所において,国,県,町及び土地改良区が集まり,喜界第二地下ダム見直し状況について説明および意見交換が行われた。当初のダム軸(南堤)路線上に透水性の高い軟質砂岩が確認されたことから路線を変更し,R6ダム委員会の了承を得たことの報告を受けた。
また,平行して進められているファームポンド造成工事や送水管工事の状況報告もあり,附帯県営事業との調整事項も再確認した。
今後,国営事業との連絡調整や協議案件がより多くなるため,密な情報共有に努め,円滑な事業推進を図りたい。
奄美地域「畑地かんがい・土地改良区」基盤強化対策セミナー(徳之島事務所)
12月4日,徳之島事務所大会議室で県土改連主催により,奄美地域「畑地かんがい・土地改良区」基盤強化対策セミナーが開催され,各大島支庁管内5土地改良区職員,大島管内農村整備課職員及び土改連職員併せて23名が参加した。
セミナーでは,大島管内各改良区の課題である水利用組合の設立・運営について,曽於南部土地改良区の黒石事務局長から講演があり,大変好評であった。
徳之島事務所農村整備課としても今後も積極的に支援・参加していきたい。
稲作文化の継承(餅つき編)(沖永良部事務所)
12月7日,知名町余多公民館において余多字主催で餅つきが行われ,沖永良部事務所農村整備課から職員2名が参加した。
もち米は地元小学生を含む集落住民が,田植えや稲刈りを行い収穫したもので,子どもたちは重い杵を振り上げ一生懸命餅つきを行っていた。
余多字では,集落内でかつて行われていた稲作を後世に継承する目的で平成24年からこの活動を行っており,餅は住民に振る舞われ,皆おいしそうに頬張っていた。
最後には,小学生から豊作祈願「稲すり節」「作田の米」のお礼踊りの披露があり,参加者で観覧した。
今後も積極的にイベントに参加し,事業PRに努めたい。
地籍調査事業の新調査手法について学ぶ研修会を開催(農地保全課)
12月5日,市町村自治会館にて,第2回地籍調査事業研修会を開催し,事業主体である市町村の担当者20名が参加した。本庁担当者から,地籍調査に係る認証承認申請の諸手続き等について説明を行ったほか,地籍アドバイザーから,準則の改定に伴う一筆地調査と測量の留意事項について講演があった。
地籍調査事業は,第7次十箇年計画の中間年に当たり,準則の改定が行われている。参加者は,認証承認申請のポイントや,改定に伴う調査手法の変更点等について学んだ。
県建設業青年部会との意見交換会で課題を討議(農地保全課)
12月17日,県建設センターにて,県建設業青年部会と県公共3部との意見交換会が開催された。青年部会からは会長・役員ら35名,県からは土木部次長ほか20名が出席し,入札,発注,積算及び施工管理などについて意見交換を行った。その後,参加者が4班に分かれ,「働き方改革」と「持続可能な建設業の在り方」をテーマにグループ討議が行われ,週休2日の取組やICTの必要性などについて意見が交わされた。
受発注者間で現状や,課題をについて共通認識を持つ良い機会となった。

水土里情報システム及びUAVの操作について学ぶ研修会を開催(農地保全課)
12月25日から26日の2日間,県土地改良会館及び吉田屋内多目的運動場にて水土里情報システム及びUAV運用研修会を開催した。
本研修会は水土里情報システムの利用促進とUAVに関する知識の習得を目的として行っており,県職員17名が参加し,水土里情報システムに関する機能や操作方法をはじめUAVの利用に関する基礎知識や遵守すべき法令等について学んだ。UAV操作実習においては,実際の資格試験と同様の課題に取り組んだ。
今後も水土里情報システムの利用促進及び職員の技術力向上に努めてまいりたい。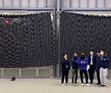
棚田セミナーin尾下の棚田の開催(農村振興課)
12月15日,棚田等の有する多面的機能等への理解促進を図るため都市住民を対象とした棚田セミナーin尾下の棚田(指宿市)を開催した。
本セミナーには県内から29名が参加し,尾下の棚田散策や草刈り,稲わら細工等を体験した。
参加者からは「棚田保全に尽力されている方々の活動がよく分かった」などの意見が聞かれ,セミナーを通じて棚田の多面的機能を広く発信することができ,良い機会となった。
今後とも,関係機関と連携しながら棚田等地域の魅力を発信してまいりたい。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください